コラム

コラム
2025年11月20日
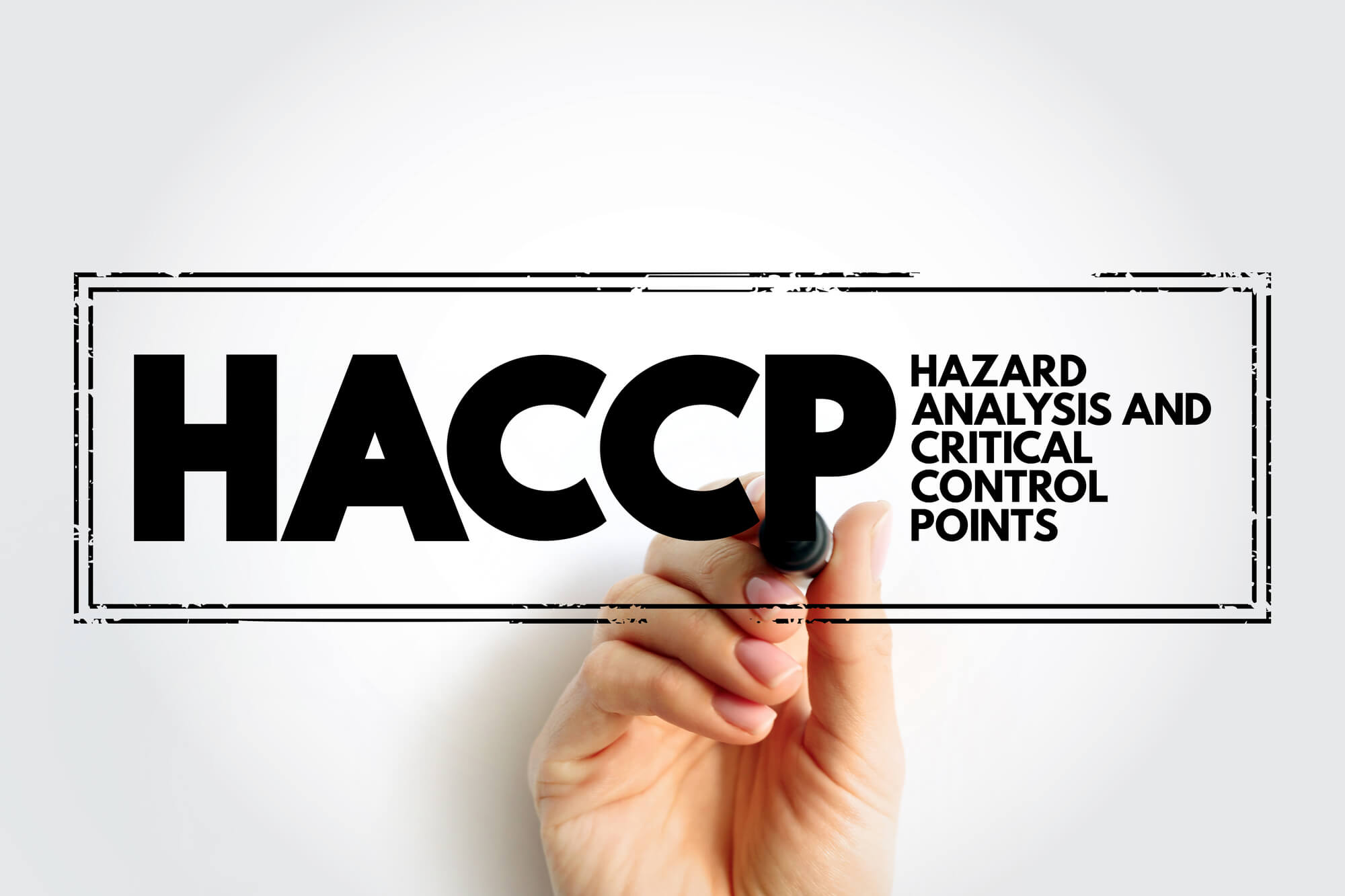
「HACCPが義務化されたと聞くけれど、一体何から手をつければいい?」
「専門用語ばかりで難しそうだし、日々の業務で手一杯で学ぶ時間もない」
HACCP導入において、このような悩みを抱えてはいませんか?
本記事では、HACCPの基本中の基本である「HACCPとは何か」という疑問から、具体的な進め方、導入のメリットまで、わかりやすく解説します。
HACCPを正しく理解し、漠然とした不安を払拭して、やるべきことを実践するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「HACCP」と聞くと、何か特別な機械を導入したり、専門家を雇ったりする必要があるのでは…と感じるかもしれません。しかし、本質はシンプルです。
ここでは、「HACCPとは何か」という言葉が持つ本来の意味から、完成品を検査する従来の衛生管理手法との違いまで解説します。
HACCPの意味
HACCP(ハサップ)とは、食品の安全を製造工程の段階から確保するための衛生管理の手法のことを指します。
HACCPは、英語の「Hazard Analysis and Critical Control Point」の頭文字をとった言葉で、日本語に訳すと「危害要因分析・重要管理点」です。
「どこに危険(Hazard)があるかを分析(Analysis)し、その危険を取り除くために最も重要な工程(Critical Control Point)を徹底的に管理する」という、予防を重視した考え方に基づいています。
この言葉を2つのパートに分解すると、より意味が理解しやすくなります。
1. Hazard Analysis(危害要因分析)
危害要因には、主に以下の3種類があります。
● 生物学的危害:サルモネラ菌やO-157といった食中毒菌、ノロウイルスなど
● 化学的危害:基準値を超えた食品添加物や残留農薬、洗浄剤のすすぎ残りなど
●物理的危害:金属片やプラスチック片、ガラス、従業員の髪の毛といった異物
これらの危険が「どの工程で発生しやすいか」をリストアップしていきます。
2. Critical Control Point(重要管理点)
重要管理点とは、上記で洗い出した危険を取り除くための最重要工程(ポイント)のことで、工場の安全を守る「急所」と言い換えてもいいでしょう。
実はこの手法、もともとは宇宙食の安全性を100%確保するためにNASA(アメリカ航空宇宙局)で開発されたもので、その信頼性の高さから今や世界標準の衛生管理手法となっています。
従来の衛生管理とHACCPの違いを、以下の表で比べてみましょう。
| 項目 | 従来の衛生管理 | HACCP |
| 目的 | 衛生的な環境を維持する | 食品に潜む危害を未然に 防ぐ |
| タイミング | 完成後(出口管理) | 製造工程中(途中管理) |
| 対象 | 完成後の一部(サンプル) | すべての製造工程 |
| 考え方 | 問題が起きてからの対処(事後対応) | 問題が起きる前に「予防」(事前予防) |
従来の衛生管理との大きな違いは、管理するタイミングにあります。従来は管理が完成した製品をチェックする「事後対応」なのに対し、HACCPは製造工程の段階で危険を管理する「事前予防」です。
HACCPは、そもそも問題のある製品が作られない仕組みを構築するため、より確実かつ効率的に安全を確保するためのものです。
もちろん、従来の衛生管理(工場の清掃や従業員の手洗いなど)はHACCPの土台となる重要なものであり、両方を組み合わせることで強固な安全体制が築けます。
「なぜHACCPが義務化されたのか」「自社も対象なのか」といった疑問は、多くの事業者が抱くところです。
ここでは、2021年6月からHACCPが完全義務化された背景と、対象となる事業者の具体的な範囲、対象事業者が何をすべきかについて詳しく解説します。
2021年6月から完全義務化された理由
義務化に至った具体的な理由は、主に以下の3点です。
1. 食品のグローバル化への対応
2. 食の安全への意識向上
3.情報共有の促進
HACCPの義務化の背景には、国際的な食品取引においてHACCPの導入が「当たり前」になっている現状があります。
海外へ食品を輸出する際にはHACCP認証が必須条件となるケースが多く、日本の食品業界全体の競争力を維持・向上させるためには、国内基準の底上げが急務となったのです。
義務化の対象となる事業者の範囲
2018年に改正された食品衛生法により、食品の安全性を確保するため、事業規模に関わらず食品を扱うすべての事業者に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められるようになりました。
ただし、事業者の規模によって、求められるHACCPの基準が異なります。
基準A:HACCPに基づく衛生管理
対象:大規模事業者、と畜場、食鳥処理場など
内容:7原則12手順(次章にてご紹介)に厳密に基づいたHACCPシステムを構築・運用する必要がある
基準B:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
対象: 従業員50人未満の小規模な製造・加工業者、飲食店、販売店、パン屋など
内容: 各業界団体が作成した「手引書」を参考に、重要管理点などを簡略化して取り組むことが認められている
自社がどちらの基準に該当するかを把握することが大切です。厚生労働省のホームページなどで、自社の業種に合った手引書があるかを確認することから始めてみてください。
対象業者がやるべきこと
対象事業者がやるべきことは主に以下の3つのシンプルなステップです。
①計画:自社の業種に合った手引書を参考に、衛生管理の計画を立てる
②実行:作成した計画に基づいて、日々の業務の中で衛生管理を実践
③記録:実行した結果を確認し、正直に記録に残す
HACCPの本質は、一度決めたルールをただ守るだけでなく、衛生管理のPDCAサイクルを回し続けることにあります。この「計画・実行・記録」という3ステップは、まさにそのサイクルを実践するための、最も基本的で重要な行動です。
HACCPの考え方を具体的に実行するための共通ルールが「7原則12手順」です。HACCP導入の設計図ともいえる重要なものですので、理解しておきましょう。
ここでは、準備段階の5つの手順から、7つの原則までを解説します。
準備段階の5手順(手順1〜5)
本格的なHACCP計画を立てる前に、その土台となる「準備段階の5つの手順」を行います。
手順1:HACCPチームの編成
まずは、HACCP導入を推進するチームを作ります。工場長だけでなく、現場の各工程に詳しい担当者など、様々な視点を持つメンバーを集めましょう。
手順2:製品説明書の作成
自社が作っている製品について、「どんな原材料を使っているか」「アレルギー物質は何か」といった情報を文書にまとめます。
手順3:意図する用途および対象となる消費者の確認
その製品が「誰に」「どのように食べられるか」を確認します。(例:そのまま食べるのか、加熱が必要か、お年寄り向けかなど)
手順4:製造工程一覧図の作成
原材料の受け入れ、製品出荷に至るまで、すべての工程の流れを一枚の図に書き出します。これが後の分析の「地図」になります。
手順5:製造工程一覧図の現場確認
作成した図が、実際の現場の動きと合っているかをチームで歩きながら確認し、ズレがあれば修正します。
7原則(手順6~12)
ここでは、手順6~12にあたる7原則について解説します。
原則1:危害要因分析の実施(手順6)
準備段階で作成した製造工程一覧図を基に、各工程に潜む健康被害の原因(危害要因)をすべて洗い出します。
原則2:重要管理点(CCP)の決定(手順7)
洗い出した危害要因の中で、その発生を防ぐための最重要工程を「重要管理点(Critical Control Point = CCP)」として決定します。
原則3:管理基準(CL)の設定(手順8)
決定した重要管理点(CCP)を安全な範囲で管理するための、具体的な数値基準である「管理基準(Critical Limit = CL)」を設定します。
原則4:モニタリング方法の設定(手順9)
設定した管理基準(CL)がきちんと守られているかを継続的に監視・測定する「モニタリング方法」を具体的に決めます。
原則5:改善措置の設定(手順10)
モニタリングの結果、管理基準(CL)から外れてしまった場合に、現場が混乱しないよう、すぐに行うべき対応(改善措置)をあらかじめ決めておきます。
原則6:検証方法の設定(手順11)
作成したHACCP計画全体が、今も有効に機能しているかを定期的に見直し、確認する「検証方法」を決めます。
原則7:記録と保存方法の設定(手順12)
これまでのすべての活動(モニタリング、改善措置、検証など)の結果を正確に記録し、それを適切に保存する方法を定めることです。
これらの記録は、保健所の監査や取引先からの要求に応えるだけでなく、万が一の際に自社の正当性を証明するための重要な文書となります。
日々の記録作業の負担を軽減し、正確性を高めるために、温度管理システムなどを活用することも有効です。
HACCPは正しく導入し運用することで、企業に多くのメリットをもたらします。
ここでは、食品事故のリスク低減はもちろん、従業員の意識向上やコスト削減、企業の信頼性向上に繋がる5つのメリットについて解説します。
1. 食品事故のリスクを低減できる
HACCP導入による最大のメリットは、食中毒や異物混入といった重大な食品事故の発生リスクを低減できることです。
HACCPは問題が発生してから対応するのではありません。製造工程に潜む危害要因をあらかじめ予測し、それを取り除くための管理ポイント(CCP)を継続的に監視する「予防型」のシステムです。
勘や経験だけに頼るのではなく、誰が作業しても一定の安全レベルを保つ仕組みを構築できます。
2. 従業員の衛生管理意識が向上する
HACCPを導入し、衛生管理のルールとその理由を明確にすることで、従業員一人ひとりの衛生管理に対する意識と責任感が向上します。
HACCP計画を策定する過程で、「温度測定」や「洗浄手順」の目的や根拠が文章として明確になります。
これにより、従業員は自分の作業が食品安全にどう貢献しているかを理解でき、主体的な行動が取れるようになるのです。
3. クレームや返品が減少しコスト削減につながる
HACCPの導入によって製品の品質が安定し、安全性が向上します。それが結果的に異物混入などのクレームや製品の返品の減少に繋がります。
HACCPは、製造工程全体を管理し、危害要因を未然に防ぐ仕組みにより、製造段階でのミスや汚染が減少し、最終製品の品質のばらつきを抑えることが可能です。
その結果、市場に出る不良品が減り、クレームやそれに伴う返品、回収といった無駄なコストを削減できます。
4. 取引先や消費者からの信頼が高まる
HACCPを導入して外部にアピールすることは、取引先や最終消費者からの信頼の獲得に繋がります。
今日の食品業界において、HACCPは「安全な食品を製造している証」として、世界共通のパスポートのような役割を果たしています。特に、品質管理に厳しい大手企業や量販店との取引においては、HACCPの導入が取引の前提条件となることも少なくありません。
5. 業務の効率化と見える化が実現する
HACCP計画を策定する過程で、自社の製造工程を徹底的に見直すことにより、これまで気づかなかった業務の無駄が「見える化」され、生産性の向上や業務効率化に繋がります
中でも、HACCP導入の最初のステップである「製造工程一覧図の作成」や「危害要因分析」は、自社の業務プロセスをゼロから見つめ直す良い機会です。各工程の目的や手順を改めて分析することで、改善のヒントが見つかります。
今回は、HACCPの基本的な考え方から義務化の背景、具体的な7原則12手順、導入による5つのメリットまで解説しました。
HACCPは、食中毒などのリスクから自社を守り、生産効率や従業員の意識を高め、顧客からの信頼を獲得するための重要な役割を担います。
HACCPの7原則の中でも重要であり、多くの食品事業者で重要管理点(CCP)となるのが「温度管理」です。食品の安全を確保する上で、正確な温度管理とその記録は欠かせません。
温度管理を手書きで記録している現場も多くあるのが現状ですが、HACCPで求められる「信頼性の高い記録」という観点からは大きなリスクになります。
そこで、おすすめしたいのが「太平洋工業株式会社」が提供する【温タイム】です。当社の温タイムは、これらの課題解決に寄与します。
センサーが自動で温度を計測・記録し、データはクラウドに保存されるため、ヒューマンエラーの心配がありません。
また、記録の手間を大幅に削減できるだけでなく、万が一設定した温度から外れた場合にはアラートで知らせる機能もあり、より確実な衛生管理を実現できます。
まずは自社の「温度管理」の見直しから始めてみませんか?
当社スタッフが貴社の状況を詳しくお伺いし、運用に沿ったご提案をいたしますので、ぜひお問い合わせください。
太平洋工業(株)新規事業推進部
【販売・利用申込み・
契約に関するお問い合わせ】
営業企画グループ
【製品に関するお問い合わせ】
(操作・設定、故障・不具合等)
プロダクトサポートグループ
受付時間:営業時間内(平日9-12時、13-17時、指定休業日除く)